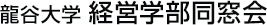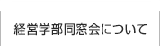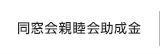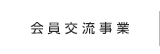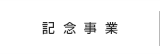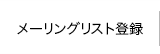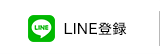経営学部同窓会事務局便りNO.2
- 東英産業株式会社 寺本英樹 代表取締役社長
現役学生を前にして「君たちの時代」と題して熱弁を振るう -
前回(10/3)の米田社長に続き、経営学部同窓会役員の第2弾として、10月31日(火)4講時(15:00-16:30)2号館201教室に於いて龍谷大学経営学部寺島教授「実践・キャリア形成論Ⅱ」の授業で、東英産業株式会社代表取締役社長の寺本英樹氏が大学の講師を務められました。
同氏は、経営学部同窓会常務理事でもあり、日頃の企業経営を通して、2050年の我が日本がどのような国に移行していこうとしているのか、また学生達にこれからあなた達が何を考え、生きていかなければならないのか、その視点は、グローバルスタンダードで人生を考え、キラッと光る自分しか持っていないものをエネルギーを使って磨かなければならない。人間として生まれてきたからには、自分の良さを活かし、人の役に立ち、社会に役立ち、人に喜ばれる人間となって欲しいと日頃の厳しい経営哲学から体得された人生訓等について、また資料から何を悟るか(危機への対応)をも含めた講義が行われた。学生達には、ものの見方として、分厚いカラー版資料集が全員に配布されました。その一部をご紹介しておきます。
1) 今日的な世界各国の経済成長(GDP:国内総生産)の比較。
2) 2050年度に向かい経済大国化するBRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)の めざましい経済成長率とその背景。
3) 2005年の日本の貿易立国から投資立国への国際収支の変遷(世界は日本に投資をしていないため今後日本経済は厳 しくなること)。
4) インフレがもたらす資産の目減り現象(例えば1%のインフレが2005年には資産運用の大敵で、数字的に所得が高額に なっても実質的所得が上がっていない貧しさへの実感)。
5) 日本は生産年齢人口(15〜64歳)ドル・円の通貨価値はほぼ人口に比例して、今後人口の減少に従って円安/ドル高が2019年度に向かっていること。
6) 日本の公共事業投資額がイギリスの1.4倍に対し8.7と非常に高いことは、公債発行額の依存度も高く、日本は、2006年度一日当たり約237億円の利払い、1時間当たり約10億円、1分当たり約1,645万円の利息を国民が負担している減少であることなど日本の財政事情や財政及び債務残高の国際比較。
7) 官の弊害としては、イギリスBBCとNHKの受信料徴収の民主的な考え方や徴収方法。
8) 日本の公務員の給料(国会議員には1人あたり8,000万円を支給し、米国の約3倍)。
9) 日本の公務員労働者数は少なく、企画事業にのみ担当し、あとは下請けの公益法人等に依存する構図となり、官市場に事業に関しては実質的には就労者が多いこと。
10) 日本の外務省の役割の弱さとODA(日本政府開発援助)のあり方。
11) 水と環境問題が将来の生命危機につながる中東でこれまでの半世紀に4億の人口増になっており、アラビア半島での死海では、毎年1.2mづつ水位が下がっていることや、北京では雲に向かって5〜6先発のミサイルを発射しヨウカ銀やドライアイスを使い雨を降らしている。日本もその内、雨が降らなくなるのではないか。将来水問題は、燃料以上に深刻となる。
以上のように講義のほんの一部のみを紹介しましたが、本日講義を受けた学生達が、これからの日本で生活していく上で、今後のどのような視点を持ち、どのようにデータを読み活用していくのか。地球的規模での基準を見すえて、自分しかできない点を磨きだす方策について、実践経営者が見た世の動きの判断の仕方・視点について、直接講義で教え・考えさせる内容であったと思う。寺本氏は、学生達に物の見方・考え方を自分の物としてほしいと一言一言に「君たちの時代」について、90分があっという間に過ぎるほどに熱弁を込めた。 学生達は、ただ大学で学んでいるだけでなく、日本の将来の危機感をもはらんだ社会的環境の中で、如何にどんなに小さくても自分しかできないものを自分探しを行い、自分で磨き、社会で役に立ち、実践できる人間として生きていくべきかを改めて噛みしめるように感じ取っていたのではないかと思った。
文責:経営学部同窓会事務局長 辻川淳一